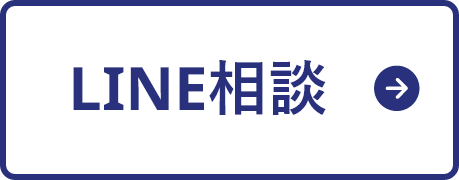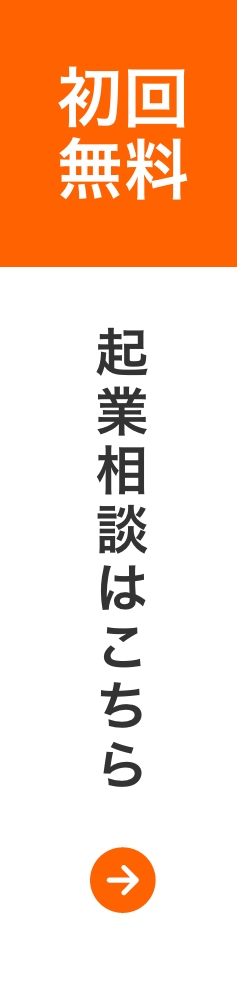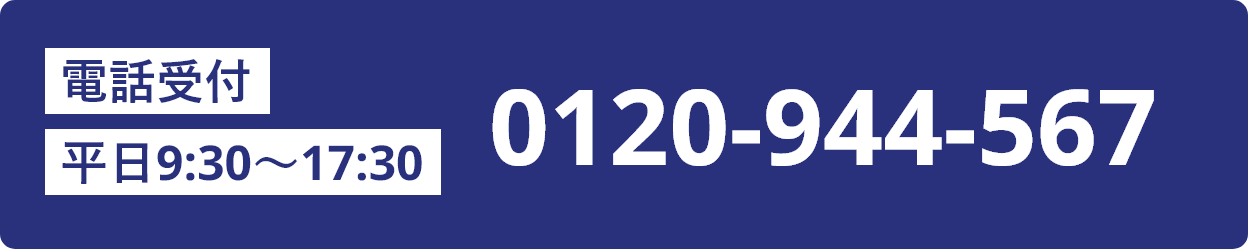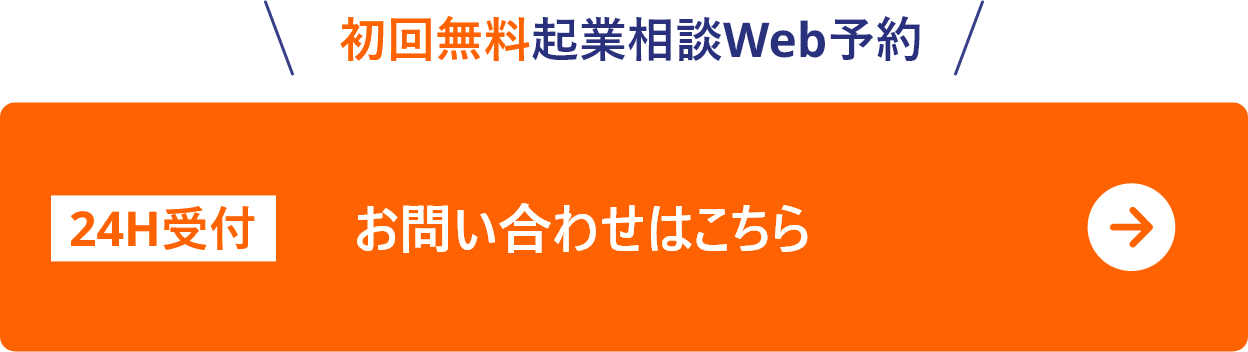個人事業主が自宅をオフィスとして使っている時の税務調査で注意するポイント
2025年08月28日
2025年08月28日

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は個人事業主が自宅をオフィスとして使っている時の税務調査で注意するポイントについて整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
なぜ自宅兼事務所は税務調査で注目されるのか
個人事業主の方が自宅を事務所として利用する場合、家賃や水道光熱費、通信費などの一部を必要経費として計上することが認められています。これを家事按分(かじあんぶん)といいます。
ではなぜ、この家事按分が税務調査で注目されるのでしょうか。それは、プライベートな生活費と事業の経費との線引きが難しく、「本当にそれは事業の経費ですか?」と疑われやすいからです。特に調査官は、家事按分が適切に行われているか、その根拠は何かを厳しく見てきます。
家事按分の基本的な考え方
家事按分で最も大切なのは、客観的で合理的な根拠に基づいて計算することです。調査官から「この割合はどうやって計算したのですか?」と聞かれたとき、自信を持って回答できるよう準備しておく必要があります。
代表的な按分基準には「面積」と「使用実態」があります。
①面積を基準にする費用
地代家賃や固定資産税、火災保険料といった建物そのものにかかる費用は、事業で利用しているスペースの広さに応じて按分するのが基本です。事業専用の部屋やスペースが、家全体に対してどれくらいの割合を占めるかで計算します。
根拠として、自宅の間取り図などを提示できると良いでしょう。「何となく半分」といった曖昧な基準では、経費として認められない可能性が高くなります。また、洗面所、居間など共用する部分は除いて、専ら事業用に使用する部分で計算してください。
②使用実態を基準にする費用
水道光熱費や通信費など、日々の活動に伴って発生する費用は、その使用実態に応じて按分するのが合理的です。
代表的な基準の一つが「利用時間」です。例えば、1週間のうち事業を行っている時間の割合を算出し、それを按分の根拠とします。また、職種によっては単純な時間割合では実態と合わないこともあります。ITエンジニアのように、明らかに電力消費量が多いといった場合は、その使用状況を示す客観的な資料を用意することで、より実態に即した割合での計上が認められる可能性もあります。
【お客様の事例】いつ税務調査が来ても良いように準備しているケース
弊社のお客様であるITエンジニアの方は、ご自身の持ち家の一室を仕事部屋として利用し、独立当初から税務調査に備えた準備をされています。
まず、自宅の間取り図から仕事部屋の面積を測定し、事業で使用する割合を30%と明確に算出しました。この割合に基づき、固定資産税、火災保険料の支払額の一部を経費として計上しています。
また、電気代については、複数のサーバーやPCを24時間稼働させる日もあるため、床面積の割合より高い60%に設定。その根拠として、スマートメーターで時間帯別の電力使用量を記録し、明らかに事業用の機器が稼働している時間帯のデータを示すことができるようにしています。
このように、費用の種類によって「面積」や「使用実態」といった異なる基準を使い分け、それぞれ客観的な資料に基づいて割合を算出しておくことが、将来のリスクへの最善の備えとなります。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。