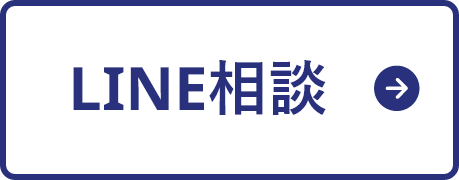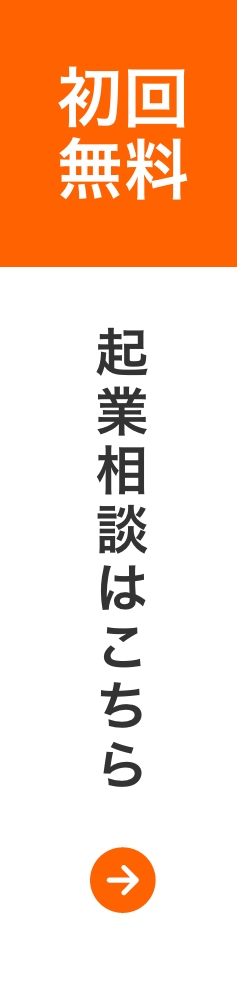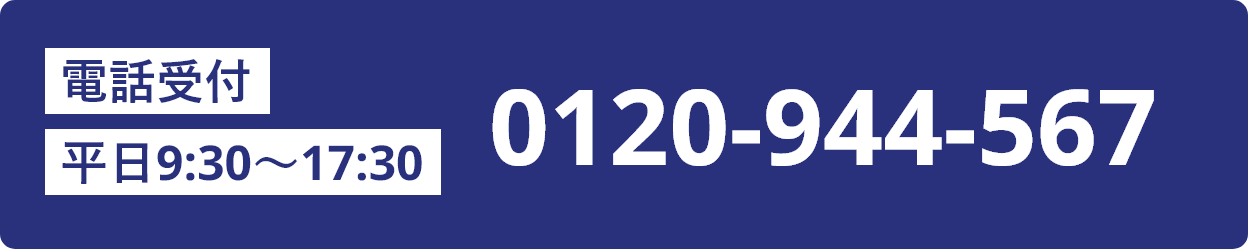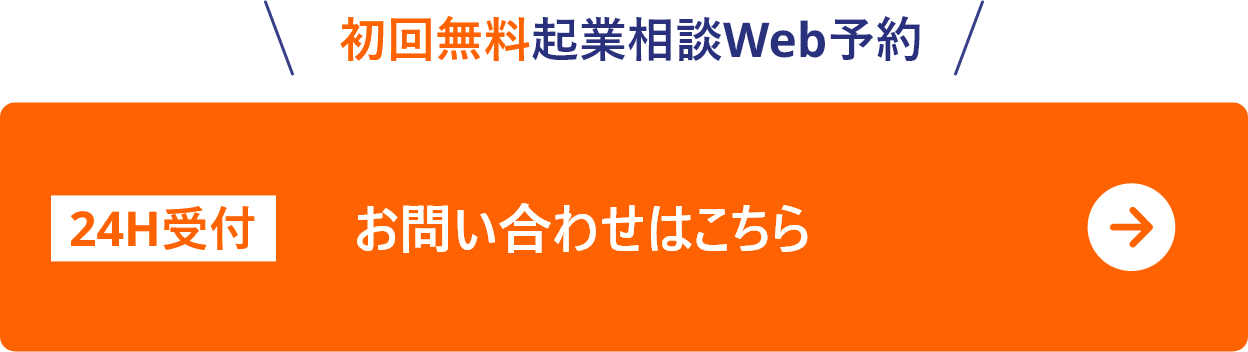法人成りで、個人から法人に資産を移すとき要注意!消費税の思わぬ負担とは
2025年10月20日
2025年11月14日
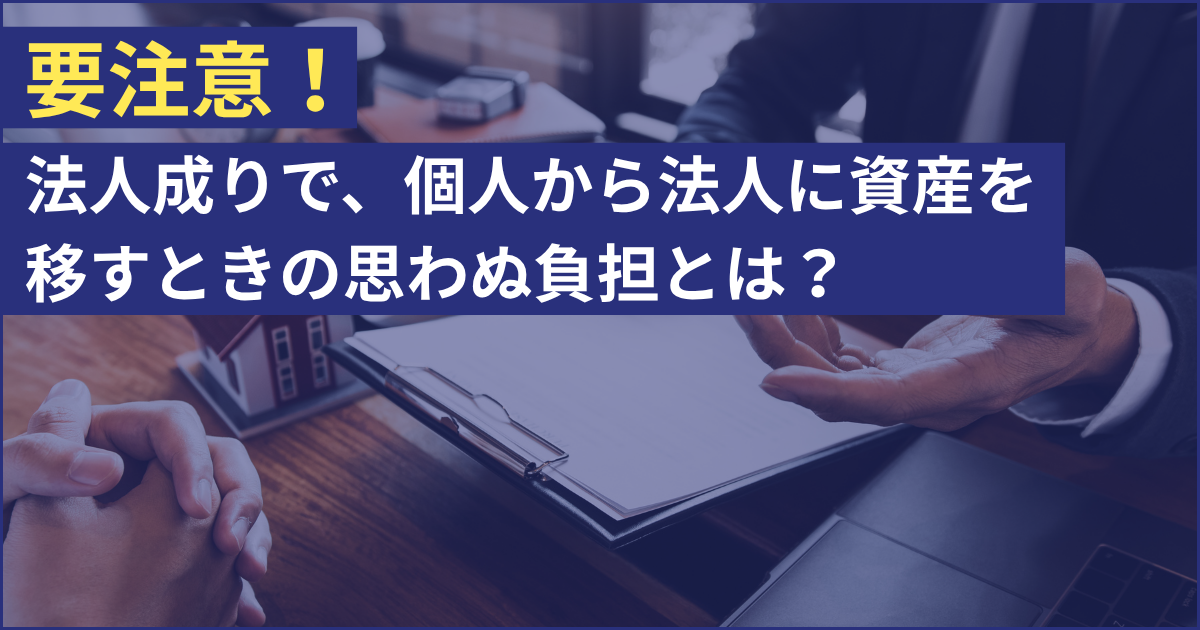
こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は「法人成りで、個人から法人に資産を移すときの消費税に関する注意点」について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
1. 法人成り時の「資産移転」とは
法人成りをする際、個人事業で使用していた事業用の資産(例:車両運搬具、機械装置、工具器具備品、建物など)を、新設法人に引き継ぐことが一般的です。
この引き継ぎ方法は主に以下の2つです。
1.個人から法人への「売却」
2.個人から法人への「現物出資」
2. 資産の「売却」に伴う二重の税負担
個人事業主が新設法人に対し、事業用資産を時価で「売却」する場合、この取引は「課税資産の譲渡」に該当し、消費税と所得税(譲渡所得)の二つの税負担が発生する可能性があります。
(1)消費税の負担:売却時に納税義務が発生する場合がある
個人事業主が課税事業者である場合、法人から受け取った売却代金に含まれる消費税を、税務署に納税する義務が生じます。
- 例: 帳簿価額100万円、時価150万円(税抜)の車両を法人に売却
- 売却対価: 150万円 × 1.10(消費税率10%)= 165万円(税込)
- 個人事業主が納める消費税: 15万円(原則として売却にかかる消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引いた額)
多くの場合、新設法人に資産を移転する時期は個人事業の最後の事業年度です。この売却取引によって、多額の消費税の納税義務が急に発生し、資金繰りを圧迫する可能性があります。
(2)所得税の負担:譲渡所得が発生する場合がある
個人が法人に資産を売却し、売却価額が資産の帳簿価額(未償却残高)を上回る場合、その差額に対して「譲渡所得」が発生し、所得税・住民税の課税対象となります。
計算式: 譲渡価額 - (取得費+譲渡費用) = 譲渡所得
例: 取得価額300万円、減価償却費累計額200万円の機械を、時価200万円で売却した場合
o帳簿価額(未償却残高):300万円-200万円 = 100万円
o譲渡所得:200万円-100万円 = 100万円(譲渡所得には50万円の特別控除あり)
差引50万円は、個人事業主の事業所得など他の所得と合算され、総合課税として課税されます(土地・建物などの譲渡所得は分離課税)。事業所得が多い年に高額資産を売却すると、税率の高い税金がかかることになります。
(3) 新設法人の負担:消費税の「仕入税額控除」ができない場合がある
新設法人は、個人から資産を買い入れた際、その代金に含まれる消費税(上記例の15万円)を「仮払い消費税」として処理し、将来の消費税の納税額から控除(仕入税額控除)するのが原則です。
しかし、新設法人は通常、設立直後の2年間は消費税の「免税事業者」を選択することが可能です。この免税事業者を選択している場合、買い入れ時に支払った消費税(仕入税額)を控除することができません。
•法人は消費税分を余分に支払い、
•個人は消費税分を納税する
結果として、個人・法人グループ全体で考えると、資金が社外に流出する「二重の負担」のような状態になってしまいます。
3.「現物出資」の消費税の取り扱い
現物出資は、個人から法人への「資産の譲渡」の一種であることに変わりはありません。したがって、原則として現物出資も「対価を得て行う資産の譲渡」として消費税の課税対象となります。
(1)消費税の課税標準(基準となる金額)について
通常、消費税は取引における「対価」に対して課されますが、現物出資の場合は 取得する株式の時価 が課税標準となります。
例:個人事業主が1,000万円相当の事業用建物を会社に現物出資した場合
その対価として、会社から1,000万円分の株式を受け取る
⇒この場合、1,000万円が消費税の課税標準 となり、これに対して消費税(原則10%)が課されます。
現物出資を行う場合は、その資産の内容や価額について、事前に税理士と綿密に確認することが不可欠です。
4. 実務上の注意点と具体的な対策
多額の税負担を避けるための対策は以下の通りです。
対策1: 法人設立初年度から「課税事業者」を選択する(法人側の対応)
もし個人から法人への「売却」を選択せざるを得ない場合や、高額な資産を移転する場合には、新設法人側で設立初年度からあえて「課税事業者」を選択することを検討します。
課税事業者となることで、個人に支払った消費税について、仕入税額控除が可能となり、法人側に発生する消費税の還付を受けることが出来ます。
ただし、課税事業者を選択すると、以後2年間(一定の場合は3年間)は免税事業者に戻れないため、今後の売上や仕入れの計画を総合的に考慮して判断する必要があります。
対策2: 売却価額の決定
「売却」の場合、個人と法人が身内であるため、恣意的な価格設定をしないよう、適正な時価(中古資産の市場価格や専門家の評価額など)で取引を行う必要があります。
適正な時価を上回るまたは下回る場合は、税務上、寄附金や役員賞与として認定され、別の税金問題を引き起こす可能性があるため要注意です。
4. まとめ
法人成りは一大イベントですが、税務上の手続きを誤ると、せっかくのメリットが損なわれてしまう可能性があります。
特に事業用資産の移転は、個人事業主の消費税の納税義務と、新設法人の仕入税額控除の可否という二つの論点が絡み合い、非常に複雑です。
法人成りをご検討の際は、手続きを進める前に、必ず専門家である税理士にご相談ください。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。