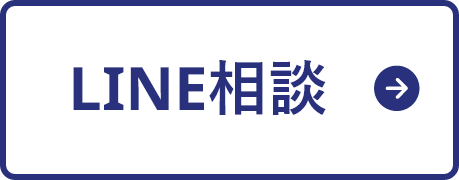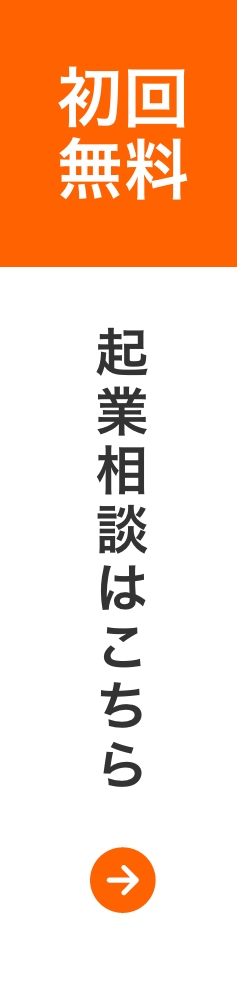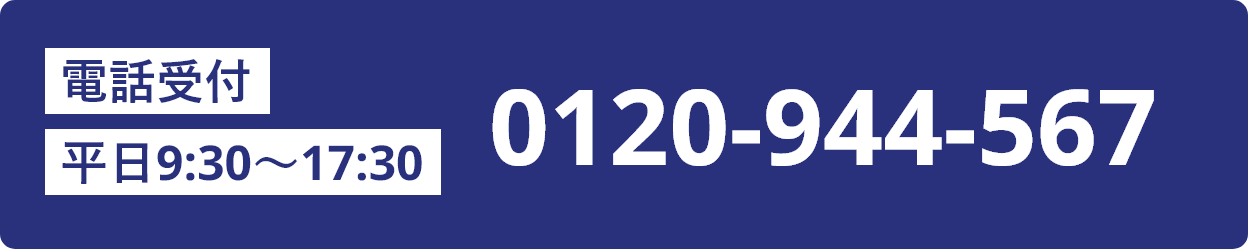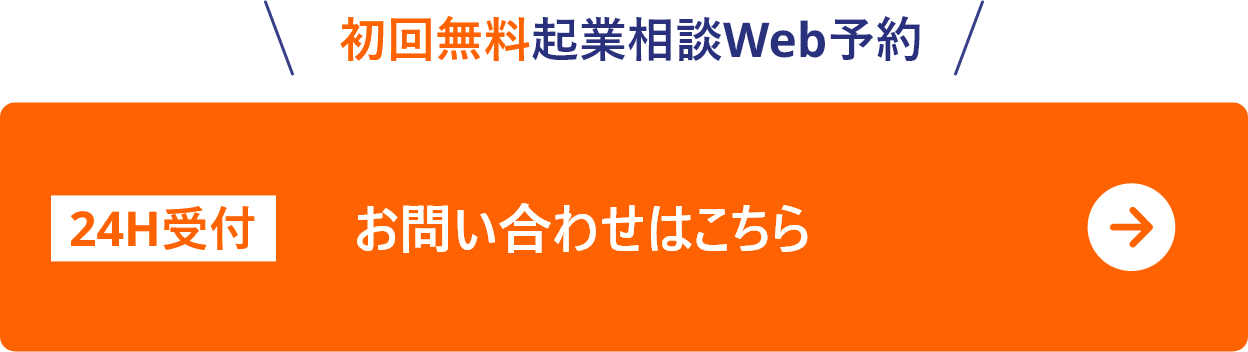起業時の「開業費」の正しい扱いと注意点!
2025年11月05日
2025年11月05日
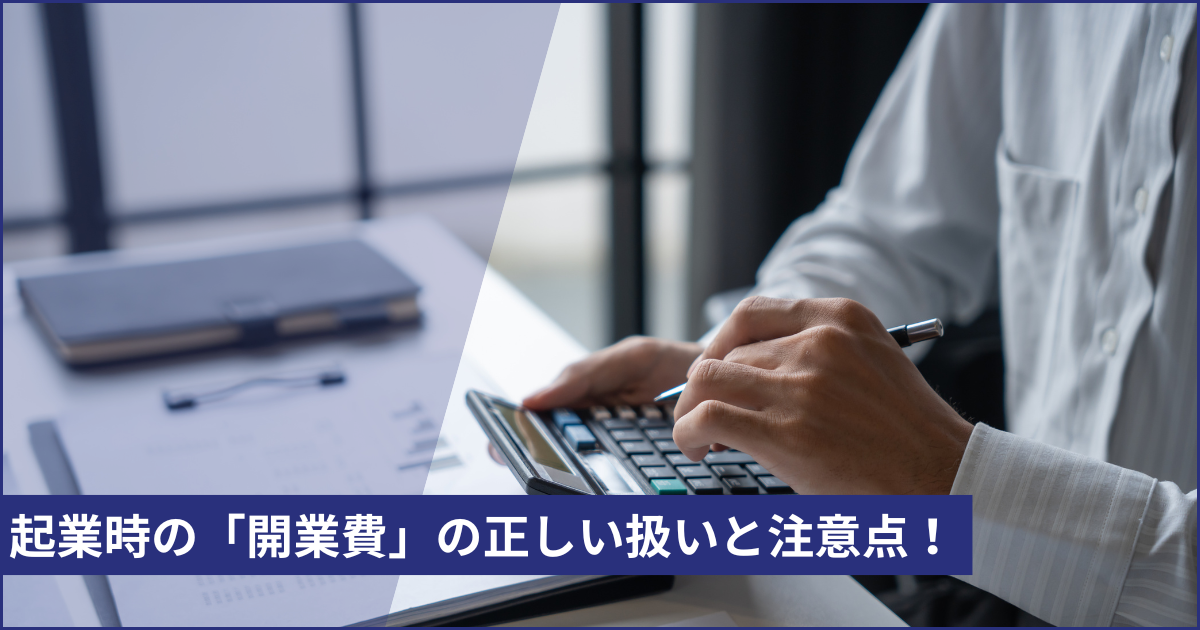
こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は起業時の「開業費(創立費)」の正しい扱いと注意点について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。
会社を設立したり個人事業を始めるとき、準備段階でさまざまな支出が発生しますよね。 たとえば、名刺やチラシの作成費、事務所の契約費用、登記にかかる印紙代など。
これらの支出は通常の経費処理と少し異なる点があり、事前に知識を身に付けておかないと思わぬ失敗を招くことがあります。
実際にあった事例として、
・「開業費(創立費)」に計上すべきものを誤って設立後の「経費」として処理してしまい、後の節税対策に支障が出たケース
・逆に、設立後の経費にすべき支出を「開業費(創立費)」としてしまったために、税務調査で指摘を受けたケース
上記事例のケースでは処理を間違えたことで余計な税金を支払うことになったり、税務署とのやり取りで多大な時間と労力を費やしたりといった失敗は少なくありません。
これらの「設立前の支出」をどのように経理処理すべきかをこのブログでは紹介いたします。
【開業費と創立費の違い】
会社(法人)を設立する際、準備段階で支出した費用は大きく分けて「創立費」と「開業費」の2つに分類されます。これらはどちらも税法上の「繰延資産」として扱われ、経理処理の方法や節税効果の面でメリットがありますが、対象となる支出の時期が異なります。
また、個人事業主は創立費と開業費を分けるのではなく、開業前後に支出した費用をまとめて開業費として計上致します。
【創立費とは】(法人のみ)
会社設立のために支出した費用で、設立登記が完了するまでに発生したものが創立費に該当いたします。
例:設立登記のための登録免許税(印紙代)、 設立に関する専門家(司法書士など)への報酬、定款の認証費用、設立準備の打ち合わせ費用や交通費等
【開業費とは】(法人と個人)
開業費は、会社設立後から事業を開始するまでの間に、「開業準備のために特別に」支出した費用を指します。個人事業主の場合は、事業開始日までの準備費用がすべて開業費(一部例外あり)になります。
例:開業に伴い支出した消耗品や接待交際費、広告宣伝費等が該当致します。
※開業費(創立費)に該当しないもの
・個人的な支出…生活費、私的な飲食費
・資産の取得…車両や機械の購入は開業費とは別に資産計上
【開業費(創立費)として計上するメリット】
開業費(創立費)は一度に費用化せず、「繰延資産」として計上し、任意のタイミングで経費化できます。つまり利益調整の「節税カード」として使える資産です。
たとえば、、、
・初年度に利益が出そう→全額償却して節税
・赤字が見込まれる→翌年以降に償却して利益圧縮
などと戦略的に使用することができ、将来の納税額を抑えることが出来ます!
開業前後は何かとバタバタしますが、どんな小さな支出でも後で「開業費(創立費)」として扱える可能性がございます。
そのためにも、領収書や請求書は必ず残しておきましょう!後から経費にできるかどうかの判断や、税務署への説明に役立ちます。
今回の記事が皆様のお役に立てると幸いです。疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。